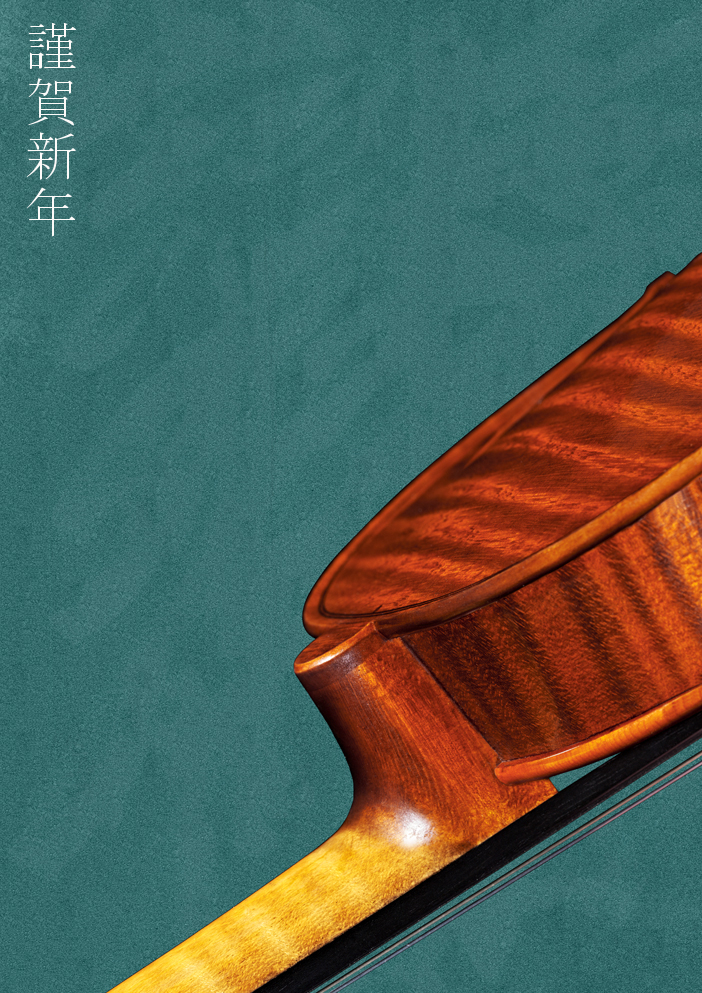ストラディバリのマンドリン~Mandolino Coristo~
先日からクレモナのバイオリン博物館に、ストラディバリが製作したマンドリンが里帰りしているので観に行ってきた。 ミラノのバイオリン製作学校時代に、楽器史の授業ではギター科の生徒が大半を占めていた為、リュートやマンドリンの歴史を重点的に教えていたが、いかんせん真面目に学校に通っていなかったため、今になってマンドリンの知識が乏しい事を後悔してしまうほど、印象に残るマンドリンであった。 このマンドリンは、1700~1710年の間に製作され、現存する2台のストラディバリのマンドリンのうちの1台。もう1台は1680年に製作されたもので、アメリカのサウス・ダコタ大学国立音楽博物館に所蔵されている。珍しい事に、どちらもストラディバリの工房製とされるオリジナルのケースが付属している。 このマンドリンは現代の見慣れたマンドリンとはかなり違った造形をしている。 マンドリンの祖先であるマンドラと同じ造形になっており、特に、長く曲線を描くペグボックスは、リュートやマンドラの祖先ウードから続く古典的な造形になっている。 マンドリンは1600年代にマンドラから発展した楽器で、発展の過渡期には「ロンバルディア型」「トスカーナ型」「ローマ型」「フィレンツェ型」「ナポリ型」など沢山の型が生まれ、それぞれの利点が集約されて現代の「モダンマンドリン」へと至る。 極初期にクレモナ・ブレーシャ型と呼ばれる物も短期間だけ存在したが、今回のストラディバリのマンドリンはそれとは大きく違い、ナポリでビナッチャ家が完成させた「モダンマンドリン」が生まれる100年程前、ミラノではMonzino家がマンドリンを進化させていく前の「初期ミラノ型」に特徴が当てはまる。 しかし、本来は初期ミラノ型は6弦の単弦、4弦の単弦、または12弦6コース(複弦)などが一般的だったようだが、ストラディバリが残した設計図の裏面に駒のデザインが残されており、8弦4コース+単弦1弦の5音で設計していたようで、当時としてはとても珍しい。そして現在では単弦1弦用のペグが取り外されて、一般的な8弦4コースだけになっている。 特徴的な楽器中心部の細工、サウンドホールロゼッタは、精密さに欠けるところがある。一方、もう1台のサウス・ダコタ博物館の方のサウンドホールロゼッタの細工はとても精密で美しい。 サウス・ダコタ博物館の方は1680年の製作ということは、ストラディバリが新しい工房に移った年、後に右腕となって活躍する長男オモボノ・ストラディバリが1歳の時であり、ストラディバリ本人製作の可能性が高い。 今回のマンドリンは1700~1710年の製作なので、既に息子たちが仕事を精力的に手伝い、大量に楽器を生産している時期であり、本人の手があまり入っていないのかもしれない。 *外注に出していた可能性も十分にあるが。 サウス・ダコタ博物館所蔵のマンドリン1680年のロゼッタ ストラディバリ製作バロックギター1679年のロゼッタ 余談だが、このマンドリンの呼び名で数日悩まされることになった。 このマンドリンはMandolino Coristoと表記されてきた。そして英語ではChoral Mandolinと訳されてきたのだが、この「Coristo」という単語に悩まされた。 と言うのも、こう呼ばれるのはストラディバリのマンドリンだけである。 この表記は、楽器本体ではなく、ストラディバリが残した設計図に直筆で表記されている事に由来する。 「Coristo」を直訳すると合唱をする人となる。そこから英語でもChoralと訳されたのだと思われる。また、イタリア語の古語として「音叉」「音程をとる笛」の事を指す。 しかし合唱用・合奏専用のマンドリンと言うのも他に類を見なければ、マンドリンで他の楽器が音程をとっていたとは到底考えられないのである。 散々調べた結果、恐らくではあるが、複弦の事をイタリア語で「Cori」と数える。4cori 6coriと。ここから派生して、複弦のマンドリンと言う意味を込めて「Coristo」とストラディバリが名付け、設計図に表記したのではないだろうか。 先述したように、この時代の初期ミラノ型は6弦単弦などが一般的だったようなので、「複弦」をあえて強調したのだと思われる。 **そもそもなのだが「Coristo」という単語は標準イタリア語では誤りである。文法上、正しくは「Corista」で、-aで終わりながら男性名詞となる。ストラディバリの時代は筆記において標準イタリア語が広まってはいたが、明確な指針がない時代なので、古文にこういう事はまま有るのだが。因みに、1861年の調査において、話し言葉における標準語普及率は10%と言う記録がある。 しかし何と言っても、このストラディバリのマンドリンの一番の特徴は、ボディーが他のマンドリンより圧倒的に細い事である。「マンドリン」と説明がなければ、マンドリンとは思いつかないほどに細い。この形状も他に類を見ないのである。 ナポリでビナッチャ家が完成させたモダンマンドリンに辿り着く過程で、初期ミラノ型マンドリンなどが廃れた理由の一つが、音の不明瞭さに有ると言われる。 現存する2つのマンドリンが設計されたのは1680年、丁度ストラディバリがバイオリン族でも音の進化を求めて試行錯誤していた時代であり、ギターやリュートなど沢山の注文が舞い込みだした時代である。 楽器のボディーを細く設計することで、甲高くより明瞭な音質を目指したのであろうか。 もしかするとこのマンドリンの形状は、新たな時代と新たな顧客へ向けて製作した、ストラディバリの音への飽くなき探究心の名残なのかもしれない。 ーーーーーーーーーーーーーー 西村翔太郎1983年 京都府に生まれ、9歳より長崎県で育つ。吹奏楽でトランペットを演奏していたことから楽器製作を志す。偶然テレビで見たオイストラフのドキュメンタリー番組に影響を受け、ヴァイオリンに興味を持つ。国内外の製作家を取材するなど製作家への道を模索しながら、高校時代に独学で2本のヴァイオリンを作り上げる。2002年 ガリンベルティを筆頭とするミラノ派のスタイルへの憧れから、ミラノ市立ヴァイオリン製作学校に入学。製作をパオラ・ヴェッキオ、ジョルジョ・カッシアーニ両氏に、ニス塗装技術をマルコ・イメール・ピッチノッティ氏に師事。2006年 クレモナに移住。クレモナトリエンナーレで最高位を獲得したダヴィデ・ソーラ氏のヴァイオリンに感銘を受け、この年から同氏に師事。2010年イタリア国内弦楽器製作コンクール ヴァイオリン部門で優勝と同時にヴィオラ部門で第3位受賞。2014年シンガポールにて、政府関係者や各国大使の前で自身が製作したカルテットでのコンサートを催す。2018年クレモナバイオリン博物館、音響・化学研究所によるANIMAプロジェクトの主要研究員を務める。2018年よりマレーシア・コタキナバルにて、ボランティア活動として子供達の楽器の修理やカンファレンスを行う。CultralViolinMakingCremona会員関西弦楽器製作者協会会員主な楽器使用者アレクサンダー・スプテル氏(ソリスト・元SSOコンサートマスター)森下幸次 氏 (ソリスト・大阪交響楽団コンサートマスター)木村正貴 氏 (東京交響楽団フォアシュピーラー)立木茂 氏 (ビオリスト・弦楽器指導者協会理事長)
Honor
ヴィオラがまた新たな演奏家さんのもとへ旅立ちました。 世界中でコンサート&レコーディングをされている立木茂氏の傍らに、 このヴィオラがいてくれることを、光栄に思います。 世界中で、音楽教育や音楽支援に携わっていらっしゃる方でもあり、 私が今進めている、東南アジア諸国への支援など、 一緒に音楽を必要としている子供たちの元へ音楽を届けられたらと、胸弾ませています。大変、素敵なご縁となりました。 Profile 立木茂 氏 ヴィオラ奏者 一般社団法人日本弦楽器指導者協会理事長ベルリンのカラヤンアカデミーでベルリンフィル首席ヴィオラ奏者のJ.カポーネに師事、その後パリでB.パスキエのもとで学ぶ。ドイツ国内のオーケストラで活動した後、ブラジルのブラジリア音楽院で7年間教授を務める。その間、ブラジリア国立交響楽団にて首席ヴィオラ奏者を歴任。1991年より、メキシコシティで黒沼ユリ子音楽院の副校長を務め、同時に、黒沼ユリ子弦楽トリオのメンバーとして世界各地で演奏活動を行う。 ーーーーーーーーーーーーー 西村翔太郎1983年 京都府に生まれ、9歳より長崎県で育つ。吹奏楽でトランペットを演奏していたことから楽器製作を志す。偶然テレビで見たオイストラフのドキュメンタリー番組に影響を受け、ヴァイオリンに興味を持つ。国内外の製作家を取材するなど製作家への道を模索しながら、高校時代に独学で2本のヴァイオリンを作り上げる。2002年 ガリンベルティを筆頭とするミラノ派のスタイルへの憧れから、ミラノ市立ヴァイオリン製作学校に入学。製作をパオラ・ヴェッキオ、ジョルジョ・カッシアーニ両氏に、ニス塗装技術をマルコ・イメール・ピッチノッティ氏に師事。2006年 クレモナに移住。クレモナトリエンナーレで最高位を獲得したダヴィデ・ソーラ氏のヴァイオリンに感銘を受け、この年から同氏に師事。2010年イタリア国内弦楽器製作コンクール ヴァイオリン部門で優勝と同時にヴィオラ部門で第3位受賞。2014年シンガポールにて、政府関係者や各国大使の前で自身が製作したカルテットでのコンサートを催す。2018年クレモナバイオリン博物館、音響・化学研究所によるANIMAプロジェクトの主要研究員を務める。2018年よりマレーシア・コタキナバルにて、ボランティア活動として子供達の楽器の修理やカンファレンスを行う。CultralViolinMakingCremona会員関西弦楽器製作者協会会員 主な楽器使用者アレクサンダー・スプテル氏(ソリスト・元SSOコンサートマスター)森下幸次 氏 (ソリスト・大阪交響楽団コンサートマスター)木村正貴 氏 (東京交響楽団フォアシュピーラー)立木茂 氏 (ビオリスト・弦楽器指導者協会理事長)
It’s a Brand New Year
明けましておめでとう御座います。 昨年は世界中を飛び回ること、8回の海外出張となり、 世界中へバイオリン文化を届けることが出来ました。 今年は、また新たな2つの国で企画が進行中です。 この企画は今後、ライフワークになるのではと思っています。 また今年も知らない土地で新たな出会いが待っていると思うと、 力が湧いてきます。 この企画には、皆様の中に 私がお力添えをお願いする方もいらっしゃるかと思いますが、 今年もどうぞ、宜しくお願い致します。 ーーーーーーーーーーーー 西村翔太郎1983年 京都府に生まれ、9歳より長崎県で育つ。吹奏楽でトランペットを演奏していたことから楽器製作を志す。偶然テレビで見たオイストラフのドキュメンタリー番組に影響を受け、ヴァイオリンに興味を持つ。国内外の製作家を取材するなど製作家への道を模索しながら、高校時代に独学で2本のヴァイオリンを作り上げる。2002年 ガリンベルティを筆頭とするミラノ派のスタイルへの憧れから、ミラノ市立ヴァイオリン製作学校に入学。製作をパオラ・ヴェッキオ、ジョルジョ・カッシアーニ両氏に、ニス塗装技術をマルコ・イメール・ピッチノッティ氏に師事。2006年 クレモナに移住。クレモナトリエンナーレで最高位を獲得したダヴィデ・ソーラ氏のヴァイオリンに感銘を受け、この年から同氏に師事。2010年イタリア国内弦楽器製作コンクール ヴァイオリン部門で優勝と同時にヴィオラ部門で第3位受賞。2014年シンガポールにて、政府関係者や各国大使の前で自身が製作したカルテットでのコンサートを催す。2018年クレモナバイオリン博物館、音響・化学研究所によるANIMAプロジェクトの主要研究員を務める。2018年よりマレーシア・コタキナバルにて、ボランティア活動として子供達の楽器の修理やカンファレンスを行う。CultralViolinMakingCremona会員関西弦楽器製作者協会会員主な楽器使用者アレクサンダー・スプテル氏(ソリスト・元SSOコンサートマスター)森下幸次 氏 (ソリスト・大阪交響楽団コンサートマスター)木村正貴 氏 (東京交響楽団フォアシュピーラー)立木茂 氏 (ビオリスト・弦楽器指導者協会理事長)
クリスマスコンサート 2017
「音楽の贈り物~世界へ羽ばたく子供たちのために~」と題して、シンガポールから始まったこの企画も第三弾となりました。音楽は「音」で出来ています。音は楽器が周りの空気を震わせ、それが鼓膜を震わせた時に音になり、音楽が生まれます。一つの震えが、他のものに伝わって、もう一つのものが同じ震えをすることを、「共鳴」と言います。なにも、人の鼓膜だけが共鳴するわけではありません。人の心も共鳴します。音楽家が心を震わせて音楽を奏でる時、聴いている人の心も震えます。この心の震えは音楽が止んでも、止まりません。心の震えは、また他の場所で他の人の心を震わせたり、子供たちの心のなかで、希望の音へと変わると信じています。今年も音楽を受け取ってくれた子供たちが、とても素直に喜んでくれました。その屈託ない笑顔は、私達への最高のクリスマスプレゼントとなりました。 ーーーーーーーーーーーー 西村翔太郎1983年 京都府に生まれ、9歳より長崎県で育つ。吹奏楽でトランペットを演奏していたことから楽器製作を志す。偶然テレビで見たオイストラフのドキュメンタリー番組に影響を受け、ヴァイオリンに興味を持つ。国内外の製作家を取材するなど製作家への道を模索しながら、高校時代に独学で2本のヴァイオリンを作り上げる。2002年 ガリンベルティを筆頭とするミラノ派のスタイルへの憧れから、ミラノ市立ヴァイオリン製作学校に入学。製作をパオラ・ヴェッキオ、ジョルジョ・カッシアーニ両氏に、ニス塗装技術をマルコ・イメール・ピッチノッティ氏に師事。2006年 クレモナに移住。クレモナトリエンナーレで最高位を獲得したダヴィデ・ソーラ氏のヴァイオリンに感銘を受け、この年から同氏に師事。2010年イタリア国内弦楽器製作コンクール ヴァイオリン部門で優勝と同時にヴィオラ部門で第3位受賞。2014年シンガポールにて、政府関係者や各国大使の前で自身が製作したカルテットでのコンサートを催す。2018年クレモナバイオリン博物館、音響・化学研究所によるANIMAプロジェクトの主要研究員を務める。2018年よりマレーシア・コタキナバルにて、ボランティア活動として子供達の楽器の修理やカンファレンスを行う。CultralViolinMakingCremona会員関西弦楽器製作者協会会員主な楽器使用者アレクサンダー・スプテル氏(ソリスト・元SSOコンサートマスター)森下幸次 氏 (ソリスト・大阪交響楽団コンサートマスター)木村正貴 氏 (東京交響楽団フォアシュピーラー)立木茂 氏 (ビオリスト・弦楽器指導者協会理事長)
夕暮の雲のように ~Viola 39cm mod.Andrea Guarneri~
small Viola 39cm mod.Andrea Guarneri Salb cut back like a "Sunset Clouds" 「大理石」のような裏板も、ニスを塗ると柔らかくなり 「夕暮れの雲」の様になりました。 製作風景 ーーーーーーーーーーーー 西村翔太郎1983年 京都府に生まれ、9歳より長崎県で育つ。吹奏楽でトランペットを演奏していたことから楽器製作を志す。偶然テレビで見たオイストラフのドキュメンタリー番組に影響を受け、ヴァイオリンに興味を持つ。国内外の製作家を取材するなど製作家への道を模索しながら、高校時代に独学で2本のヴァイオリンを作り上げる。2002年 ガリンベルティを筆頭とするミラノ派のスタイルへの憧れから、ミラノ市立ヴァイオリン製作学校に入学。製作をパオラ・ヴェッキオ、ジョルジョ・カッシアーニ両氏に、ニス塗装技術をマルコ・イメール・ピッチノッティ氏に師事。2006年 クレモナに移住。クレモナトリエンナーレで最高位を獲得したダヴィデ・ソーラ氏のヴァイオリンに感銘を受け、この年から同氏に師事。2010年イタリア国内弦楽器製作コンクール ヴァイオリン部門で優勝と同時にヴィオラ部門で第3位受賞。2014年シンガポールにて、政府関係者や各国大使の前で自身が製作したカルテットでのコンサートを催す。2018年クレモナバイオリン博物館、音響・化学研究所によるANIMAプロジェクトの主要研究員を務める。2018年よりマレーシア・コタキナバルにて、ボランティア活動として子供達の楽器の修理やカンファレンスを行う。CultralViolinMakingCremona会員関西弦楽器製作者協会会員主な楽器使用者アレクサンダー・スプテル氏(ソリスト・元SSOコンサートマスター)森下幸次 氏 (ソリスト・大阪交響楽団コンサートマスター)木村正貴 氏 (東京交響楽団フォアシュピーラー)立木茂 氏 (ビオリスト・弦楽器指導者協会理事長)