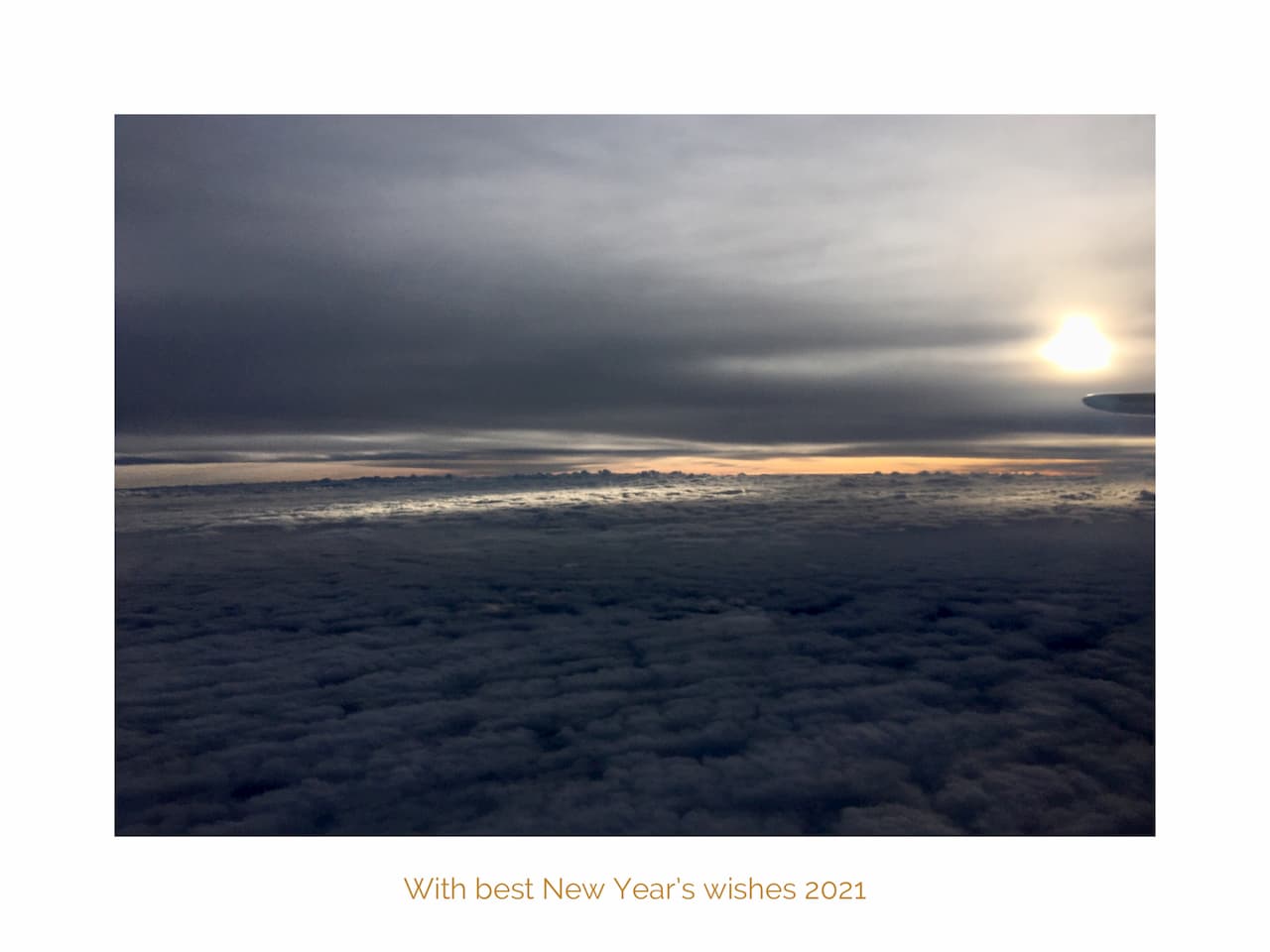音のゆりかご ~ヴェネチアとストラディバリ~
昨年の関西弦楽器製作者協会のコラムに寄稿したものを転載致します。 こんにちは。イタリアのクレモナでバイオリン製作を行っている西村翔太郎です。今年でイタリアに住んで18年が経ち、丁度人生の半分をイタリアで過ごした事になりました。イタリアの風景も既に日常となり、もはや日本の風景のほうが感慨深く感じる様になりましたが、やはりバイオリン製作という伝統工芸に携わっていると、予期せず、ある事象が突然に歴史と一つ、また一つと繋がっていき、思いもよらぬ所へと導かれ、あらためてイタリアの奥深さに瞠目させられる時があります。 2012年にクレモナのバイオリン製作家が、ユネスコ世界遺産の無形文化遺産に選ばれました。それを機に、2018年よりガリンベルティ市長の号令の下、複数あるクレモナの製作家協会やグループを統括するDistretto Culturale della Liuteria(バイオリン製作家ディストリクト)が立ち上がりました。このディストリクトにはユネスコやカリパルマ銀行からの支援金が下りており、ワークショップや講演会、ストラディバリやガルネリの弾き比べ演奏会など、製作家に向けたイベントが一気に増えることになりました。その中の活動の一つとして、研究プロジェクトが有ります。計画案を提出して認可が下り、進行中のプロジェクトが現在3つあります。バイオリン博物館主導のバンク・オブ・サウンド、バイオリン製作学校主導のT.A.R.L.Oそして私が所属する A.N.I.M.A です。この A.N.I.M.Aは、パヴィア大学とミラノ工科大学と共同で、数ある伝統的な木材処理を、最新の分子生物学と音響学の二つの側面から解析していくプロジェクトです。木材処理は製作の様々な過程で行われているのですが、音質改善や見た目の改良、処理後の加工の容易さなど、目的も様々です。しかし、その効果と影響を科学/化学的に評価したものは殆どなく、感覚や経験則に頼るしかありませんでした。そこを明らかにしていくのがこのプロジェクトです。研究の初期段階から既に予想とは反する解析結果が複数出ていて、驚いている所です。 そんなグラフと数字を見つめる日々の中、ある論文が目に留まりました。昨年発表された、台湾とニューヨークの研究チームがストラディバリの楽器の木質を解析した論文なのですが、異常な数値の天然由来のナトリウムが検出されていました。そして同時期に製作された他の国の楽器では検出されていませんでした。それを読んだとき、得も言われぬ感覚に陥りました。グラフと数字を読んでいる自分が、歴史と一つ、一つと繋がり、思わぬ方向へ流されていく感覚です。 クレモナはイタリア最長の河川、ポー川に面した街です。ストラディバリが活躍していた当時、川は物資の輸送の要、今で言う高速道路の役割を果たしており、数多くの大都市が河川沿いに発展しました。ストラディバリなど、クレモナの製作家たちはポー川で結ばれたヴェネツィアから運ばれてくる木を使ってバイオリンを製作をしたと言われてきました。その事について初めて言及したのが、史上初めてのバイオリンコレクターでもある、コッツィオ・ディ・サラブーエ伯爵(1755-1840)です。彼はストラディバリやガルネリを大量に集め、その偏執的な性格からCarteggioと呼ばれる膨大な量の記録を残しました。その中で、「ストラディバリが使用していた木はヴェネツィアのアルセナーレに水中貯木して寝かした木を使用していた」という記述があるのです。しかし、これが書かれたのはストラディバリが死んで40年ほど後、ストラディバリのニスのレシピの記述など、今では明らかに間違いであると判る記述もあるので、信憑性がそれほど高いものでありませんでした。 コッツィオ・ディ・サラブーエ伯爵(1755-1840) ヴェネツィアの「アルセナーレ」とは造船所の事を指します。造船といってもヴェネツィア名物のゴンドラを作るところではなく、主にガレー船といわれる、輸送船または海戦用の軍艦を作っていたところです。 ヴェネチア共和国は700年代から1700年代後半まで約1000年続いた、歴史上最も長く続いた共和国で、その安定した政治体制から別名、「La Reppublica Serenissima平穏の共和国」 と呼ばれていました。しかし実情は、中東への飽くなき覇権拡大から絶えず他国と交戦し、交易を拡大、国を挙げての中東への観光事業を行うなど、それはそれは騒がしい都市でした。 そして、その基幹を担っていたのが、造船業です。輸送を担った巨大なガレー船はもちろん全てが木製で大量の木材が必要となりました。その需要に応えるためヴェネチアには、その圧倒的な領土と財力で、東は東欧から、北はアルプスから大量に木材が昼夜を問わず運ばれて来ていました。運ばれてきた材木はまず、ヴェネツィア南部で税関もあるザッテレ地区に運ばれていました。ザッテレとはイタリア語で「いかだ」「木材運搬用いかだ」の事。木材業者が地名の由来となっています。そのザッテレ地区で仕分けした後、ヴェネツィア東部の造船所アルセナーレに運ばれていました。 1700年代の記録によると、1年間に42万本もの木材が運び込まれていました。既にヴェネチア共和国が衰退し始めていた時代でこの数ですから、その旺盛さには目を見張るものが有ります。当時のアルセナーレの記録に、「木材をむやみに損失した者は、死を持って償う」との文言があり、これでもまだまだ木材が不足していた様子がうかがえます。アルセナーレの職人たちが木を削る様子は、ダンテの「神曲」地獄篇の中でも美しく謳われています。 この運ばれてきた大量の木材は製材を待つ間、水中貯木と言って水の中に浮かせていました。こうすることで急激な乾燥での割れを防いだり、水中微生物の効能への期待など、日本でも行われている伝統的な方法です。 造船所アルセナーレ ガレー船 木材を運搬するイカダZattera このアルセナーレに水中貯木されていた木の中で、交易でクレモナに運ばれてきた木をストラディバリが使っていたと言われてきたのです。 昨年のストラディバリの木質を解析した研究では、天然由来のナトリウムが大量に検出されました。大量にナトリウムが木質の中にまで入り込むにはある程度漬け込む必要があります。木材研究では、水中貯木では丸太の芯材にまで均等に水が浸透するには18か月かかるとされる研究があります。そしてヴェネツィアのアルセナーレは海水です。その事から今回の結果は、ストラディバリがアルセナーレで水中貯木していた木を使っていた証拠になり得ます。 そして、この研究には続きがあります。このナトリウム成分が長期間の演奏による木質の変化(リグニン・ヘミセルロースの崩壊)を促進しており、ストラディバリの独特な音質の要因になっていると結論付けています。 これが事実だとすれば、1000年の繁栄を誇った共和国が衰退していく中で、 最後に大輪の花を咲かせるかのように、文化が大きく花開き人々が狂乱していたヴェネチアの片隅で、職人たちの働く音だけが響く造船所が、バイオリンの「音のゆりかご」になっていたようです。 最新の解析技術と数字を見つめながら、意識が歴史の彼方へ流されていき、 まるでアルセナーレの木の様に漂っている感覚。 まだまだクレモナからは離れられそうにありません。 今年のアルセナーレ2019「アルセナーレ」の語源はアラブ語の技術工場を意味するDaras-Sina ahから来ています。常に他国と交易を行い異文化を受け入れ、守護聖人までもエジプトから持ってきてしまうヴェネツィア。現在のアルセナーレは、現代アートと最新建築の展示会場になっていて、なんでも受け入れてきたヴェネツィアの神髄を今でも見せてくれています。 --------------------------- 西村翔太郎 1983年 京都府に生まれ、9歳より長崎県で育つ。吹奏楽でトランペットを演奏していたことから楽器製作を志す。偶然テレビで見たオイストラフのドキュメンタリー番組に影響を受け、ヴァイオリンに興味を持つ。国内外の製作家を取材するなど製作家への道を模索しながら、高校時代に独学で2本のヴァイオリンを作り上げる。2002年 ガリンベルティを筆頭とするミラノ派のスタイルへの憧れから、ミラノ市立ヴァイオリン製作学校に入学。製作をパオラ・ヴェッキオ、ジョルジョ・カッシアーニ両氏に、ニス塗装技術をマルコ・イメール・ピッチノッティ氏に師事。2006年 クレモナに移住。クレモナトリエンナーレで最高位を獲得したダヴィデ・ソーラ氏のヴァイオリンに感銘を受け、この年から同氏に師事。2010年イタリア国内弦楽器製作コンクール ヴァイオリン部門で優勝と同時にヴィオラ部門で第3位受賞。2014年シンガポールにて、政府関係者や各国大使の前で自身が製作したカルテットでのコンサートを催す。2018年クレモナバイオリン博物館、音響・化学研究所によるANIMAプロジェクトの主要研究員を務める。2018年よりマレーシア・コタキナバルにて、ボランティア活動として子供達の楽器の修理やカンファレンスを行う。CultralViolinMakingCremona会員関西弦楽器製作者協会会員 主な楽器使用者 アレクサンダー・スプテル氏 (ソリスト・元SSOコンサートマスター)森下幸次 氏 (ソリスト・大阪交響楽団コンサートマスター)木村正貴 氏 (東京交響楽団フォアシュピーラー)立木茂 氏 (ビオリスト・弦楽器指導者協会理事長)
Decollouomo ~ シャツブランドからの取材~
先日、高機能シャツブランド、Decollouomoさんから、取材をして頂きました。 子供の頃の話から、イタリアに渡った理由、そして今後の展望まで、幅広く話しをさせて頂きました。普段、このブログでは話さないような内容ですので、ご興味のある方は下記のリンクからどうぞ。 decollouomo story 08 – 西村翔太郎 氏【海外に出ていく日本人の為のシャツ!着る人のパフォーマンスと美意識のどちらも満足させるデッコーロウォモ】 ---------------- 西村翔太郎1983年 京都府に生まれ、9歳より長崎県で育つ。吹奏楽でトランペットを演奏していたことから楽器製作を志す。偶然テレビで見たオイストラフのドキュメンタリー番組に影響を受け、ヴァイオリンに興味を持つ。国内外の製作家を取材するなど製作家への道を模索しながら、高校時代に独学で2本のヴァイオリンを作り上げる。2002年 ガリンベルティを筆頭とするミラノ派のスタイルへの憧れから、ミラノ市立ヴァイオリン製作学校に入学。製作をパオラ・ヴェッキオ、ジョルジョ・カッシアーニ両氏に、ニス塗装技術をマルコ・イメール・ピッチノッティ氏に師事。2006年 クレモナに移住。クレモナトリエンナーレで最高位を獲得したダヴィデ・ソーラ氏のヴァイオリンに感銘を受け、この年から同氏に師事。2010年イタリア国内弦楽器製作コンクール ヴァイオリン部門で優勝と同時にヴィオラ部門で第3位受賞。2014年シンガポールにて、政府関係者や各国大使の前で自身が製作したカルテットでのコンサートを催す。2018年クレモナバイオリン博物館、音響・化学研究所によるANIMAプロジェクトの主要研究員を務める。2018年よりマレーシア・コタキナバルにて、ボランティア活動として子供達の楽器の修理やカンファレンスを行う。CultralViolinMakingCremona会員関西弦楽器製作者協会会員主な楽器使用者 アレクサンダー・スプテル氏(ソリスト・元SSOコンサートマスター)森下幸次 氏 (ソリスト・大阪交響楽団コンサートマスター)木村正貴 氏 (東京交響楽団フォアシュピーラー)立木茂 氏 (ビオリスト・弦楽器指導者協会理事長)
アンドレア・アマティとユダヤ人
すべてのクレモナのバイオリン製作家の祖先である、アンドレア・アマティ。彼がクレモナで初めてのバイオリン製作家であるかについては前回の記事で言及した。*前回の記事はこちらアンドレア・アマティの名前が歴史上初めて登場する資料の下りで、マルティネンゴという人物の下働きとして登場する理由について、論考とはそれてしまうために省略していたが、今回はその事について触れたいと思う。 アンドレア・アマティの名前が歴史上初めて登場するのは、1526年にFragumentorumと呼ばれる「武器所持者リスト」の中に登場する。当時、常に他国からの侵略に晒されていたクレモナの街の防衛のため、商人や職人など街中に住む庶民のうち15~50歳の男性が銃器を所持し、緊急事態には防衛の最前線に立つことが義務付けられていたのだが、Fragumentorumはその登録者リストである。 Paterの表記と、歴史上最初のAndrea Amatiの表記 まずこのリストが1937年に歴史学者の3人によって発見されたおかげで判明したことは、アンドレア・アマティの出生年が、それまで言われてきたよりもずっと以前であるという事である。1526年にFragumentorumのリストに掲載されていたということは、この時代に少なくともアンドレア・アマティは15歳以上であり、1505年より前に生まれたことになる。そして、1556年にはリストから名前が外れていることから、このときには既に50歳を過ぎていたことが解る。 そして、このリストで最も注目されるのが、Giovanni Leonardo de Martinego (以下マルティネンゴ)という人物の下働きとしてアンドレア・アマティの名前が出てくる事である。まずはこの、マルティネンゴとは何者なのかについて、諸説を検証しつつ見ていこう。リストのマルティネンゴの名前の横に「Pater」という表記があるが、「Pater」をどう解釈するかで歴史学者の間で意見が別れている。この表記はクレモナの古語のため理解が難しいのだが、まず「パーテル」と発音するのと「パテール」と発音するのかで意見が別れている。「パーテル」と発音すると、父親や雇い主という意味になり、アンドレア・アマティが下働きとして書かれているので、それなりに辻褄は合うが、書かれいている箇所が他の人では職業名が書かれている箇所なので、そこに「雇い主」と書くのは不自然に思える。ではこれを「パテール」と発音するとどうか。こちらでも意見が別れていて、イタリア語古語の「pattero」布織物商人ではないかとする意見と、クレモナの古語で「金融・質屋」の事だとする意見とがある。 どちらかを知るためには、マルティネンゴの来歴を知る必要がある。マルティネンゴの父親はMoise' de Salomone de Martinengoと下を噛みそうなぐらい長い名前の持ち主のヴェネツィア出身の銀行家で、当時ベネツィアの支配下にあったベルガモ県マルティネンゴ市から、1499年にベネツィアの支配下に入ったクレモナに移り住んだ3人の銀行家の内の一人であるという説が有力だ。当時、不当な高利貸しが横行していたクレモナで金利の調整をすることで、ベネツィアへの税金や軍事費の支払いを円滑にする事がその務めであったようだ。1509年にクレモナがベネツィア支配下から外れると、父マルティネンゴはベネツィアに戻っているのだが、マルティネンゴはそのままクレモナに残っている。この来歴を考えると、布織物商人というよりも金融業を営んでいたという方が自然である。 ここで重要なことは、布織物商人であれ金融業であれ、どちらもユダヤ人の仕事であったことである。そう、マルティネンゴはユダヤ人であった。そして、キリスト教に改宗したユダヤ人であったようである。後年、キリスト教教会に大量の寄付をしたことが記録に残っている。名前がGiovanni Leonardoと、全くユダヤ人的ではない名前を考えると、父親が既にキリスト教に改宗していた可能性もあるし、ペストなど疫病が流行るたびにユダヤ人のせいにし排斥が強まるなど、当時の世間の風潮から息子を遠ざける目的だったのかもしれない。 *この時代のクレモナでのユダヤ人の営みについては、イタリア・ユダヤ人協会のクレモナ支部のサイトに細かく記されているので、興味がある方は是非。http://www7.tau.ac.il/omeka/italjuda/items/show/865 さて、マルティネンゴの人物像を見たところで、一つの疑問が湧いてくる。何故、アンドレア・アマティはユダヤ人商人の元で楽器を製作していたのであろうか。クレモナやヴェネツィア、ブレーシャなど、ユダヤ人が集中している所にバイオリン職人も集中していた事から、ユダヤ人の間で楽器製作が行われていたため、マルティネンゴも楽器製作の技術を持っていたという説を唱えた学者もいるが、真実は定かではない。しかしもし、ユダヤ人がもともと製作の技術を持っていたのなら、プロの製作家になっていてもおかしくないが、この時代の他の楽器製作者のリストを見ても、歴史上ユダヤ人の名前を持った製作家がいないことを考えると、この説は少し疑わしい。少なくと、マルティネンゴもプロの製作家ではなかったことは先述した通りである。しかしこの当時、バイオリン製作家の主な顧客がユダヤ人であったことは事実である。 どういう事か。次はイタリアにおけるユダヤ人について見ていこう。この当時のイタリアは他のヨーロッパ諸国と同じく、ユダヤ人への弾圧を強めいていた。一般的にユダヤ人隔離地区を「ゲットー」と呼ぶが、これはベネツィアで1516年に初めて厳格にユダヤ人を隔離した地区が作られ、それが旧製鉄所跡地であり、ベネチア弁で製鉄所をゲットーと呼んだ事がユダヤ人居住区「ゲットー」の語源とされている。ベネツィアは数々の歴史的発明をしているが、負の歴史も生んでいた。話はそれたが、このようにイタリアでもユダヤ人は弾圧されていた。 しかし、そのような社会状況の中でも、クレモナはユダヤ人に対してとても寛容な街で、特に1441年のヴィスコンティ家とスフォルツァ家の結婚の後、貴族たちに帯同していた金融業(主に軍資金調達)を生業とするユダヤ人がそのまま住み着き、ユダヤ人人口が増えていった。クレモナのこの当時のユダヤ人への寛容さを象徴するものが、大聖堂の中にある。大聖堂の身廊をぐるりと囲むフレスコ画の中に、ヘブライ文字で描かれている部分があるのだ。これは大変に珍しく、クレモナのユダヤ人についての文献では必ず言及されている。さらにユダヤ人の大聖堂への立ち入りはミサ中であっても自由であったようだ。 *キリスト殺しの犯人だと迫害をしていたユダヤ人の文字を大聖堂の聖書の場面を描くフレスコ画に挿入するという事は、博愛主義というよりも、キリストの人生はヘブライ文化の中を通ってきたという事実を正面から受け止める、宗教的寛容性や客観性からのように感じられて面白い。 大聖堂のフレスコ画。奥の石版にヘブライ語が描かれている いくらイタリアの地方によって寛容さに差異があっても、イタリア全土においてユダヤ人が就ける職業だけは厳しく制限されていた。金利を取ることを良しとされていなかったキリスト教世界において、金融業はユダヤ人の主な生業であったが、それ以外に就ける職業では、行商や製造業に限らていた。しかし文化的な活動は許されていた。その中でも特筆すべき職業が音楽家であった。 イタリアで最初期のオーケストラが組織されたのはベネツィアだが、その中でもユダヤ人音楽家で編成されたものがとても人気を博していて、イギリス宮廷やフランス宮廷などにも呼ばれて演奏していた。イタリア音楽の発展に大きく寄与した、マントヴァのゴンザーガ家もユダヤ人音楽家を手厚く保護しており、国外の演奏旅行も支援した他、キリスト教会での演奏も許可していた。その中にユダヤ人バイオリニストのSolomone Rossiがいる。このように当時はイタリアの楽団がヨーロッパ中でもてはやされていたが、その中に沢山のユダヤ人がいた。ユダヤ人音楽家がイタリア音楽の普及、ひいては生まれたばかりの楽器バイオリンをヨーロッパ中へと広めるのに大きな役割を担っていた。 ユダヤ人バイオリニストSolomone Rossi さて、話をアンドレア・アマティに戻すと、この様な時代背景から何故マルティネンゴの元で働いていたのかについて一つの推測が導き出されるのである。まだ駆け出しのバイオリン職人だったアンドレア・アマティは、最大の顧客であるユダヤ人とのコネクションが必要だった為に、マルティネンゴの元で働いていたのでないかという事である。アマティ自身がユダヤ人だったのではないかという説を唱える人もいる。しかしこれはあまり信憑性が薄いと個人的には考えている。何故なら、1500年代後半にクレモナがスペイン支配下に入ると、融和的であったクレモナでも反ユダヤ人の風潮が強まり、1597年にフェリペ2世により新しい反ユダヤ法が制定されると、ゲットーが積極的に作られ始め、ユダヤ人の人口は半分以下にまで下がる。更にユダヤ人の文化的な活動や職業を禁止し、政治の中枢にまでいたユダヤ人ですらもクレモナを追放されている。しかしそんな中、アマティ家は住居を制限されることもなければ、より精力的に活動しているのである。 クレモナの大聖堂のすぐ脇にある、旧ゲットー地区via Torriani このように、バイオリン製作の歴史にユダヤ人は深く関わっている。日本人の私には到底理解し得ない、彼らが歩んできた歴史と独自の民族性が、ヨーロッパ音楽に豊潤をもたらした事を忘れてはならないと思う。 ーーーーーーーーーーーー 西村翔太郎1983年 京都府に生まれ、9歳より長崎県で育つ。吹奏楽でトランペットを演奏していたことから楽器製作を志す。偶然テレビで見たオイストラフのドキュメンタリー番組に影響を受け、ヴァイオリンに興味を持つ。国内外の製作家を取材するなど製作家への道を模索しながら、高校時代に独学で2本のヴァイオリンを作り上げる。2002年 ガリンベルティを筆頭とするミラノ派のスタイルへの憧れから、ミラノ市立ヴァイオリン製作学校に入学。製作をパオラ・ヴェッキオ、ジョルジョ・カッシアーニ両氏に、ニス塗装技術をマルコ・イメール・ピッチノッティ氏に師事。2006年 クレモナに移住。クレモナトリエンナーレで最高位を獲得したダヴィデ・ソーラ氏のヴァイオリンに感銘を受け、この年から同氏に師事。2010年イタリア国内弦楽器製作コンクール ヴァイオリン部門で優勝と同時にヴィオラ部門で第3位受賞。2014年シンガポールにて、政府関係者や各国大使の前で自身が製作したカルテットでのコンサートを催す。2018年クレモナバイオリン博物館、音響・化学研究所によるANIMAプロジェクトの主要研究員を務める。2018年よりマレーシア・コタキナバルにて、ボランティア活動として子供達の楽器の修理やカンファレンスを行う。CultralViolinMakingCremona会員関西弦楽器製作者協会会員主な楽器使用者アレクサンダー・スプテル氏(ソリスト・元SSOコンサートマスター)森下幸次 氏 (ソリスト・大阪交響楽団コンサートマスター)木村正貴 氏 (東京交響楽団フォアシュピーラー)立木茂 氏 (ビオリスト・弦楽器指導者協会理事長)
ヴィオローネのジョバンニ ~歴史に埋もれたチェロ職人?~
昨年末、関西弦楽器製作者協会のコラムに書かせて頂い内容が大変好評だったため、更に写真を加えてこちらに転載致します。 イタリアに住んでいると、歴史の中に住んでいるという感覚が強くあります。 そのせいか、最近イタリアの歴史を掘り下げるのが趣味になりつつあります。 同じ場所で幾層にも積み重なったイタリアの歴史を掘り下げて行くと、見慣れた街並みが突然違って見えてくる瞬間があり、それがとても好きなのです。 特に、知られた歴史に名を残した偉人や歴史的な事件よりも、パスタの歴史や道の名前の由来など、少し変わった切り口から掘り下げる方が面白く、たまにブログにまとめたりもしています。 近年、クレモナでもバイオリン製作の歴史研究が盛んに行われていて、色々なことが解ってきています。アマティ家の国税調査から、武器所持者のリストから辿る製作家の年齢、果てはガルネリ家の借金事情まで・・・歴史に名を残すと恥も残るのだとよく分かった次第です。そんな偉人たちの影で、最近、私が気になって調べている事があります。 皆さんはアンドレア・アマティという名前を聞いたことが有るでしょうか。アマティ家の初代にして、クレモナのバイオリン製作の開祖とされているバイオリン製作家です。 現存する世界で一番古いバイオリン族の楽器も、アンドレア・アマティが製作したチェロです。 このチェロは1536年に注文を受け1538年までに製作された楽器とされており(サウスダコタ博物館調べ)、”THE KING”という名前がついており、フランスの王シャルル9世に38台の楽器を納めた内の一台です。 では当時、アンドレア・アマティだけがクレモナで楽器を作っていたのでしょうか。 国勢調査を辿ると、クレモナの最初の楽器製作者はStephannis detto "Nepos"です。 長く続いたフランスとの戦争が終結に向かいつつあった1507年に工房を開設しました。しかし彼は撥弦楽器(ルネッサンスギターやリュート)の製作家で、バイオリン族やガンバ族の製作家ではありませんでした。 その後、1526年の武器所持者リストにアンドレア・アマティの名前が、マルティネンゴという商人の下働きとして出てきます。これがアンドレア・アマティの最初の記録であり、クレモナで最初のバイオリン製作家の記録です。(何故、楽器職人が商人の下働きだったのかについては、ユダヤ人の歴史と関わってくるなど大変長くなるので、またの機会に。) やはり当時、バイオリン族やガンバ族の製作家はアンドレア・アマティだけだったのでしょうか。実はそうでもないようなのです。 どうやら同時期に「Maestro Giovanni dalli violoni (ヴィオローネ職人のジョバンニ)」と呼ばれた職人が、クレモナにいたようなのです。 まず、1526年の武器所持者リストの中に、アンドレア・アマティの同僚としてGiovanni Antonioという名前が出てきます。 そしてその後、1547年、マントヴァという街の大司祭が書いた、教会の収支報告書の中に名前が出てきます。小麦から魚まで、教会で消費されていた物を何処から幾らで仕入れたかを事細かく書かれているのですが、その中に「ヴィオローネ職人のジョバンニ」から、教会に務める音楽家のためにヴィオローネの弦を仕入れ、他の教区の司祭にも10本の弦を分け、分割で支払があった旨が書かれているのです。 ケンブリッジ大学の資料より そして、バイオリンの弦の購入も含めた2枚の領収書も一緒に残っていて、こちらにクレモナと記されています。 しかし、それ以外のことは何も解っていません。そして、残念ながら楽器も一台も残っていません。ヴィオローネは当時、「ヴィオローネ・ダ・ガンバ」と呼ばれる現代のコントラバスの祖先と、「ヴィオローネ・ダ・ブラッチョ」と呼ばれていたバロックチェロの、どちらに対しても用いられていた名前です。(しばしこれが混同され、ビオローネ・ダ・ガンバがチェロの祖先とする記述が散見される) 残念ながら、この呼び名からはジョバンニがどちらを製作していたのかは判別できません。 この当時のマントヴァは、後にイタリアの音楽文化発展の礎を築いた、領主グリエルモ・ゴンザーガが生まれる少し前、マントヴァ風ミサを書いた作曲家のパレストリーナも、ゴンザーガ家お抱え作曲家ジャッケス・デ・ヴェルトも、まだマントヴァには来ていません。恐らくは、ちょっとしたマドリガーレやモテット、小規模のミサ曲が演奏されていた程度であったと思われます。楽器はその声楽曲をなぞるだけの役割だったので、まさにヴィオローネがどちらの楽器か指定する必要がなかった形式の音楽です。 グリエルモ・ゴンザーガ やはり、ジョバンニがどちらの楽器の製作家だったかを辿るのは難しいかもしれません。しかし、クレモナの楽器製作の黎明期に、もう一人の製作家として「ヴィオローネ職人のジョバンニ」は確実に存在はしていたようです。 この、歴史に埋もれた製作家。もう暫く色々と調べてみようと思っています。いったい何が出てくるか。いつかまた、ブログで綴れれば良いなと思います。 かつて歴史哲学者ヴァルター・ベンヤミンが、こう書き残しました。 「無名な人々を敬う事は、有名な人々のそれより難しい。歴史の構築は無名な人々の記憶に捧げられる」 歴史に名を残した人々の少し後ろを掘り下げると、そこには「無名な人々」の営みが見えてきます。私が気になって調べだす時、そういった「無名な人々」の気配を何処かで感じているからかもしれません。 西村翔太郎 ーーーーーーーーーーー 西村翔太郎1983年 京都府に生まれ、9歳より長崎県で育つ。吹奏楽でトランペットを演奏していたことから楽器製作を志す。偶然テレビで見たオイストラフのドキュメンタリー番組に影響を受け、ヴァイオリンに興味を持つ。国内外の製作家を取材するなど製作家への道を模索しながら、高校時代に独学で2本のヴァイオリンを作り上げる。2002年 ガリンベルティを筆頭とするミラノ派のスタイルへの憧れから、ミラノ市立ヴァイオリン製作学校に入学。製作をパオラ・ヴェッキオ、ジョルジョ・カッシアーニ両氏に、ニス塗装技術をマルコ・イメール・ピッチノッティ氏に師事。2006年 クレモナに移住。クレモナトリエンナーレで最高位を獲得したダヴィデ・ソーラ氏のヴァイオリンに感銘を受け、この年から同氏に師事。2010年イタリア国内弦楽器製作コンクール ヴァイオリン部門で優勝と同時にヴィオラ部門で第3位受賞。2014年シンガポールにて、政府関係者や各国大使の前で自身が製作したカルテットでのコンサートを催す。2018年クレモナバイオリン博物館、音響・化学研究所によるANIMAプロジェクトの主要研究員を務める。2018年よりマレーシア・コタキナバルにて、ボランティア活動として子供達の楽器の修理やカンファレンスを行う。CultralViolinMakingCremona会員関西弦楽器製作者協会会員主な楽器使用者アレクサンダー・スプテル氏(ソリスト・元SSOコンサートマスター)森下幸次 氏 (ソリスト・大阪交響楽団コンサートマスター)木村正貴 氏 (東京交響楽団フォアシュピーラー)立木茂 氏 (ビオリスト・弦楽器指導者協会理事長)